皮膚科の疾患について

🔳 皮膚科一般疾患
◆皮膚炎
皮膚炎は皮膚の上層に起きた炎症で、かゆみ、水疱、発赤、腫れを生じ、多くの場合、じくじくして、かさぶたになり、鱗屑(うろこ状のくず)が生じます。原因として分かっているものには、皮膚の乾燥、特定の物質への接触、特定の薬、静脈瘤などがあります。原因と症状によって治療も異なります。
◆水虫
水虫は白癬菌という皮膚の真菌症(カビの一種)です。足の水虫は日本人の4人に1人にみられる皮膚病。 白癬菌は身体のいろいろなところに感染しますが、足白癬が60%といちばん多く、つぎに爪白癬が34%、そのほかにも体部や、股間にも感染することがあります。診断は、病変の部分に白癬菌がいることを確認することです。患部の皮膚を採取して顕微鏡で白癬菌の存在を調べます。足白癬の治療は抗真菌作用のある塗り薬を使用します。一方、爪白癬の治療は抗真菌薬の内服が第一選択ですが、最近ではしっかり透過する外用薬での治療も一般的になってきています。
◆いぼ
いぼは、ポックスウイルスによって引き起こされる伝染性の強い皮膚感染症です。体の多くの部分に出現することがありますが、かゆみや痛みを伴うことは通常ありません。診断は一般的に、いぼの外観に基づいて下されます。また、患部の皮膚からサンプルを採取して顕微鏡で調べる検査を行うこともあります。自然に消えないいぼは、クリーム剤で治療するか、凍結、焼灼、切除を単独または組み合わせて用いる処置によって取り除き、治療することができます。
◆ニキビ
ニキビは、死んだ皮膚細胞の堆積物や細菌、乾燥した皮脂などが皮膚の毛包を塞ぐことによって生じます。多くの場合、顔面、胸、肩、背中の皮膚に、黒色面皰(めんぽう)、白色面皰、吹き出物、嚢腫(のうしゅ)などの隆起が現れ、ときに膿瘍も生じます。ニキビを診断するには、皮膚の診察を行います。治療法は軽度、中等度、重度により異なります。
◆魚の目
一般的に足の裏や足の指にでき、皮膚に継続的あるいは間欠的に摩擦・圧迫の刺激を受け続けることで、その部分の角質が厚く硬くなって生じる病変(角質肥厚)です。患部は小豆くらいの大きさで皮膚が硬くなっており、中央に穴のようなくぼみがあったり、白い点が見えたりします。これが目のように見えることから「魚の目」や「鶏の目」と呼ばれます。魚の目の芯は放置しているとさらに大きくなり、強い痛みを伴うことがあるほか、外因性の滑液包炎が生じることもあるため、早めの除去が大切です。
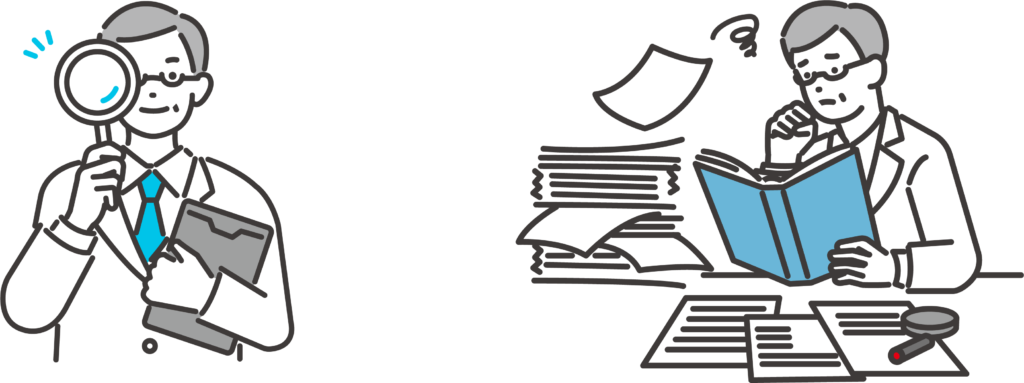
◆帯状疱疹
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウィルスで起こる皮膚の疾患です。体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。帯状疱疹の初期症状は、皮膚の痛みや違和感・かゆみです。続けて皮膚症状が現れると、やがて刺すような痛みとなり、夜も眠れないほど激しい痛みになる場合があります。帯状疱疹の治療は、原因となっているウイルスを抑える抗ウイルス薬と、痛みに対する痛み止めが中心となります。帯状疱疹を発症した、または疑いがある場合には速やかに受診し、初期段階で治療をスタートすることが重要です。
◆口唇ヘルペス
ヘルペスウイルスが原因で起こる感染症で、小さな水泡(水ぶくれ)や赤み、痛みなどの症状を伴うのが特徴です。このヘルペスが唇やその周囲にできる病気が、口唇ヘルペスです。一度感染すると体内に潜伏し続け、何らかのきっかけが引き金となって再び活動を開始することがあります。そのため口唇ヘルペスは完治が難しく、再発を繰り返す可能性が高い病気だと言えます。治療が早ければ、重症化を防げるため、ピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら出来るだけ早めに受診することが肝要です。口唇ヘルペスの治療は、抗ウイルス薬という種類の、塗り薬(外用薬)もしくは内服薬を用いて治療します。
◆やけど
皮膚に高温の液体・金属・炎や、紫外線、化学物質などが触れることにより、皮膚やその下に存在する皮下組織にダメージを引き起こす外傷のことです。やけどはダメージが及ぶ皮膚の深さによってI~III度に分類され、治療を行います。やけどの治療としては感染の予防が非常に重要です。そのため、日々傷の処置をして、受傷した皮膚を清潔に保つことが必要です。
◆虫さされ
蚊やノミなどに刺されることで生じる身近な皮膚病です。多くの虫刺されは、アレルギー性の軽い炎症反応を部分的に起こすものであり、腫れや痛みを生じます。ただし、ハチやムカデなどに繰り返し刺された場合は命に関わることがあるため注意が必要です。
多くの場合、自然に治癒しますが、かゆみが強い場合には、副腎皮質ステロイド外用薬などが使用されます。
◆伝染性膿痂疹(とびひ)
細菌による皮膚の感染症で、人にうつる病気です。掻きむしった手を介して、水ぶくれ(水疱)があっという間に全身へ広がる様子が、火事の火の粉が飛び火することに似ているため、「とびひ」と呼ばれています。症状が軽く、あまり全身に広がっていない時は抗生物質の外用薬(軟膏)で治療します。とびひが全身に広がっている場合は、外用剤に加えて抗生物質を内服します。

🔳 皮膚科アレルギー疾患
◆アトピー性皮膚炎
かゆみのある湿疹が、慢性的に良くなったり悪くなったりを繰り返す病気です。アトピー性皮膚炎では、皮膚の”バリア機能”が低下していることから、外からのアレルゲンなどの刺激が入りやすくなっており、これらが免疫細胞と結びつき、炎症を引き起こします。また、かゆみを感じる神経が皮膚の表面まで伸びてきて、かゆみを感じやすい状態となっており、掻くことによりさらにバリア機能が低下するという悪循環に陥ってしまいます。アトピー性皮膚炎の治療は、①スキンケア ②薬物療法 ③悪化要因の対策の3つが治療の基本となり、どれもが不可欠です。
◆食物アレルギー
ある特定の食べ物を食べたり、触れたりした後にアレルギー反応があらわれる疾患です。食物アレルギーの原因となる物質であるアレルゲンは、主に食べ物に含まれるタンパク質で、乳幼児期には小麦や大豆、鶏卵、牛乳などが、学童期以降では甲殻類や果物、そば、魚類、ピーナッツなどのように、加齢に伴って食物アレルギーの原因が変わっていくという特徴があります。食物アレルギーでは、症状が出ないように原因となる食品を除去する「除去療法」と、症状が出てしまったときに症状を改善させる治療があります。
◆花粉症
花粉症は、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎の中でもスギやヒノキなどの春の花粉が原因によるものが多く、主にくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、充血などが生じます。花粉症と食物アレルギーが合わさった口腔アレルギー症候群ではまれですが、アナフィラキシー反応が生じる場合があり、医師の正確な診断・治療が必要となります。
◆蕁麻疹(じんましん)
皮膚の一部がくっきりと赤く盛り上がり(膨疹)が身体のあちらこちらにできる疾患です。しばらくすると跡形もなく皮疹とかゆみが消えるという特徴があります。かゆみを伴いますが、焼けるような感じになることもあります。発症して6週間以内を「急性じんましん」、それ以上経過した場合を「慢性じんましん」と呼びます。じんましんはアレルギーが関係している場合と、物理的刺激や運動、疲労・ストレス、原因がわからない特発性などアレルギーが関係していない場合があります。治療は、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などの飲み薬や塗り薬を中心に行います。アレルギーなど原因が明らかな場合は、原因アレルゲンや刺激の回避をすることが大切です。また、勉強や仕事などのストレスや暴飲暴食、不規則な生活を避けることが重要です。
◆薬疹
薬疹は通常、薬に対するアレルギー反応によって引き起こされます。典型的な症状としては、発赤、膨らみ、水疱、じんま疹、かゆみのほか、ときに皮膚の脱落や痛みなどがあります。どの薬が発疹を引き起こしているかを特定することが必要です。

🔳 脱毛症
◆円形脱毛症
円形や楕円形に髪の毛が抜けてしまう脱毛症です。複数個所が脱毛する場合や、個々の脱毛箇所がくっついて広がり、すべての頭髪が抜ける場合などがあります。痛みなどはなく、突然一気に髪の毛が抜けることもあることから、自分では気づかず他の人からの指摘で気づくケースも多いのが特徴です。
◆男性型脱毛症(AGA)
思春期以後の男性で髪が薄くなり、年齢とともに進行する脱毛症。特に頭の上や前の毛が軟毛になる、日本人成人男性の約3人に1人にみられる症状です。原因は、思春期に体の中に増える男性ホルモンの作用によるもので、また、遺伝的な素質が関係することもあります。当院では自費の飲み薬を扱っています。
関連リンク
AGA-news:http://aga-news.jp/
万有製薬のAGA(エージーエー)に関する情報サイトです。
🔳 爪疾患
◆陥入爪・巻き爪
陥入爪とは、爪の角や側面が皮膚に食い込んでしまう状態。症状は、疼痛(痛み)、発赤(赤み)、腫脹(腫れ)などの炎症兆候で、炎症が悪化して感染が起こると、赤みと腫れが強くなり、じゅくじゅくした肉芽ができることがあります。一方、巻き爪とは、爪の先端が内側に巻いたように変形して、皮膚を挟んでしまう状態。症状は、疼痛(痛み)、発赤(赤み)、腫脹(腫れ)などの炎症兆候です。治療方法は、保険適用のフェノール法(食い込んだ爪を根元まで切除)や部分爪母摘出術(爪が生えるもとになる部分を切除)、非保険適用のワイヤー矯正(ワイヤーを通して爪の先を広げる方法)も行っております。
関連リンク
専門医と学ぶ「巻き爪・陥入爪」治療の相談室:https://medical-media.jp/
日本初の「巻き爪・陥入爪」治療に特化した情報サイトです。
🔳 ピアス
◆ファーストピアス
ピアスの穴を開けることは医療行為です。病院以外でピアスを開けた場合、感染症などのトラブルに発展することがあります。穴を開けたばかりの皮膚はとても敏感で、ピアスによっては金属アレルギーの原因にもなります。このようなトラブルを避けるために、特に初めての穴あけ(ファーストピアス)は、医療機関での処置をおすすめします。
片耳 ¥4,250 両耳¥8,500(税込価格)
※ピアスは当院で扱っているもの(誕生石、人工ダイヤ、GOLD、SILVER等 )の中よりお選びいただけます。

